はじめに|ヴェルディのクレカ情報流出事件、何が起きた?
2024年、J1クラブ・東京ヴェルディのオンラインストアを利用した一部ユーザーのクレジットカード情報が不正に取得・流出するという衝撃の事件が報道されました。
漏えいの対象となったのは2700人以上、被害総額はおよそ4200万円にのぼります。
さらに驚くべきは、犯人が外部からのハッカーではなく、システムの内部にいた元エンジニアだったという点です。
この事件は「誰でも起こり得る被害」であり、決して他人事ではありません。
本記事では、クレジットカードの専門サイト「クレピ!」としての視点から、
- 事件の概要と不正アクセスの手口
- なぜ情報が盗まれたのか?
- 私たちが今できる防衛策は?
を、わかりやすく解説します。
「知らなかった」では済まされない時代。
正しい知識と備えで、大切なカード情報を守りましょう。
第1章|東京ヴェルディのクレカ情報流出事件とは?
まずは、今回の事件の概要を振り返りましょう。
2024年、サッカーJ1リーグのクラブチーム「東京ヴェルディ」の公式オンラインストアにおいて、利用者のクレジットカード情報が不正に取得されていたことが発覚しました。
捜査の結果、次のような事実が明らかになりました。
- 犯人は、かつてサイトのメンテナンス業務を担当していたシステムエンジニア
- サイトのプログラムを改ざんし、カード情報を抜き取る仕組みを埋め込んでいた
- 入手されたカード情報は闇市場に流通し、少なくとも4200万円相当の不正利用が確認された
- ヴェルディは、漏えいの可能性がある人数を2700人以上と発表
つまりこの事件は、内部犯行によるシステム改ざんという、一般ユーザーが防ぎようのないルートでの情報漏えいでした。
「公式サイトだから安心」「大手だから大丈夫」
そうした思い込みが通用しないことを、この事件は示しています。
第2章|内部の人間が仕掛けた“改ざん”の手口とは?
今回の事件で注目されたのは、「外部からのハッキングではなく、内部の人間による不正アクセス」だった点です。
報道によると、犯人である元システムエンジニアは、ヴェルディのオンラインストアのプログラムコードを改ざん。
クレジットカードの入力画面で記入された情報が、第三者のサーバーにも送信されるように設計していたと見られます。
このような手口は、セキュリティ業界では「フォームジャッキング(Formjacking)」と呼ばれ、以下のような流れで行われます。
🔓 不正アクセスの典型的な流れ
- サイトの管理権限を持つ人物が、不正なコードをこっそり埋め込む
- ユーザーが正規のフォームにカード情報を入力
- その情報が、攻撃者が指定した外部のサーバーへ送信される
- 攻撃者は盗んだ情報を売却 or 自ら悪用
この手法の恐ろしさは、ユーザー側には一切気づかれにくいことです。
SSL化されたURLであっても、見た目は普段どおりの決済画面。
セキュリティに詳しくない限り、不正に気づくのはほぼ不可能です。
そのため、今回のような「元関係者」による犯行は、企業の管理体制そのものの甘さを突いたものといえます。
第3章|なぜ気づかれなかった?サイトの“脆弱性”と運営リスク
今回の事件が特に怖いのは、「被害が長期間、誰にも気づかれなかった」ことです。
なぜ不正なコードの存在が見抜けなかったのか――その背景には、中小規模ECサイトの運営体制の甘さがあります。
🔍 よくあるECサイトの盲点
- 外注した開発者・エンジニアがソースコードに自由にアクセスできる状態が放置されている
- コードレビューやセキュリティチェックが定期的に行われていない
- サイト改修後の検証作業が形だけになっている
- セキュリティ専門人材が社内にいない or 雇えない
こうした状況では、一度「信頼されていた人間」が不正を働いた場合、非常に気づきにくく、被害が長期化しやすいのです。
また、不正なスクリプト(簡易なプログラム)や外部送信の痕跡は、一定の知識がないとログを見ても見逃されてしまいます。
🔐 クレカを使う私たちにできること
- 大手でない通販サイトではクレカ情報の直接入力を避ける
- Apple PayやGoogle Pay、Amazon Payなどの外部決済サービスを活用
- クレカ情報はなるべく「紐付けっぱなし」にせず、都度入力 or 限定利用に切り替える
- 利用明細は毎月チェックし、見覚えのない支払いはすぐ調査
第4章では、実際に被害に遭わないために個人でできる防衛策をより具体的に紹介します。
第4章|クレジットカード情報を守る!私たちにできる5つの対策
「もう何を信用していいのかわからない」――
ヴェルディの事件を受けて、そんな声がネットでも多く見られました。
しかし私たち個人にも、今すぐできる“被害を防ぐ習慣”があります。
ここでは、クレジットカードのプロであるクレピ!が厳選した5つの防衛策を紹介します。
① 信頼できる決済サービスを使う
- 「楽天ペイ」「Amazon Pay」「PayPay」などの第三者決済サービスを選びましょう
- これらは販売元にカード情報が渡らない仕組みになっており、情報漏えいのリスクが激減します
② 利用明細を毎月チェックする
- 月に一度、カードの明細を目視で確認する習慣をつけましょう
- 少額決済でも「身に覚えのない支払い」はすぐにカード会社に連絡!
③ サイトにカードを“登録しっぱなし”にしない
- よく使うサイトでも、必要なときだけ入力する方が安全です
- 特にマイナーなECサイトでは、カードの保存機能をオフにしておきましょう
④ 不審なメール・SMSに注意する
- 「決済失敗のお知らせ」などを装って偽サイトに誘導するフィッシング詐欺が横行中
- 本物か迷ったら、メール内のリンクはクリックせず、公式アプリや公式サイトからアクセス
⑤ 利用上限額をコントロールする
- カードの利用限度額をあえて下げておくことで、万一の被害も抑えられます
- 利用限度額の変更方法はこちらの記事を参考に:
👉 楽天カードの利用可能額を増やす方法
🚨 被害にあってしまったら?まずやるべきこと
どれだけ気をつけていても、不正利用のリスクはゼロにはなりません。
万が一、身に覚えのない利用に気づいたら、すぐにカード会社へ連絡しましょう。
クレピ!としては、毎月の明細チェックを「最も現実的かつ効果的な対策」としておすすめしています。
クレジットカードは便利な反面、“情報の管理”という責任も伴う支払い手段です。
「知らなかった」では済まされないリスクに、正しい知識と習慣で備えましょう。
まとめ|“便利さ”の裏にあるリスクと、私たちができること
今回の東京ヴェルディの事件では、内部関係者による不正アクセスという、一般利用者には防ぎようのない手口が使われていました。
どんなに対策していても、情報漏えいのリスクをゼロにすることはできません。
しかし、被害に遭う可能性を下げたり、被害を最小限に抑えたりすることは可能です。
とくに意識しておきたいのは以下の3点です。
- サイトにカード情報を登録しっぱなしにしない
- 月に一度は必ず明細をチェックする
- 身に覚えのない利用があったら即連絡する
これは決して「怖がらせるための記事」ではありません。
むしろクレジットカードは正しく使えば、ポイント還元や利便性など現金よりも得する仕組みがたくさん詰まったツールです。
だからこそ、「カードを使うなら最低限の防御策を身につけておこう」
――これが、クレピ!からの結論です。

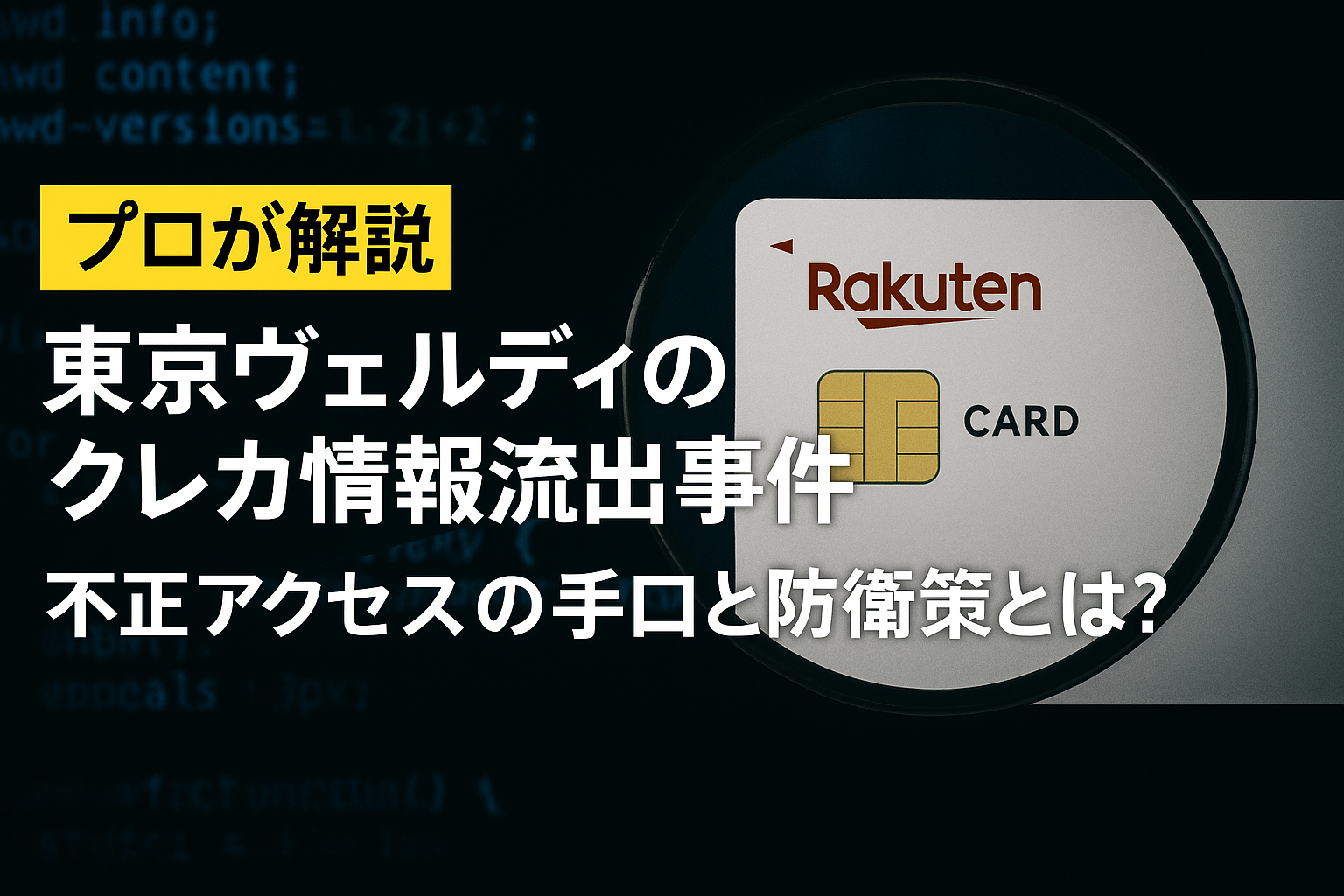
コメント